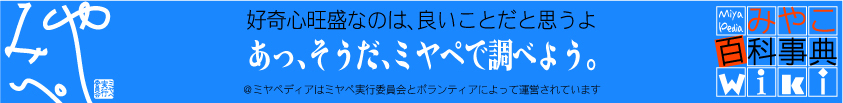千両男山
目次 |
千両男山
現在宮古に残る唯一の地酒銘柄。発売元は鍬ヶ崎下町の菱屋酒造店。創業は嘉永年間(1852)で当初は濁り酒を製造。明治34年(1901)から清酒を製造している。当初は男山ではなく「松緑」の名銘で販売した。現在の「干両男山」の名は昭和初期ころに高貴で力強い名柄にしたらどうかと当時の宮古税務署役人が名付けたという。この間一時期だけ下閉伊酒造に統合されたが、昭和初期に再び菱屋ののれんに戻り、現在に至っている。水は鍬ヶ崎日影町、金勢社付近から湧き出る地下水を井戸で汲み上げて使用。井戸付近には菱屋酒造で祀る稲荷神社がある。米は100%県産米を使用。口当たりは甘口と辛口の中間をいく「うまくち」タイプ。現在は吟醸酒をはじめ様々な手法で仕込んだ清酒を製造している。
かつての宮古の地酒
深山幽谷の隠れ滝をイメージ
- 清酒・宝滝
花輪地区から折壁地区を経て津軽石~豊間根地区を結ぶ根井沢街道と花輪街道の交差点でもある長沢の寺沢地区で、造り酒屋を営んでいたのが宝滝(現・中野酒店)である。現在の花輪地区は水田が広がる田園風景が連なる宮古有数の米作地帯だがその歴史は意外と浅く、水田の開墾が開始されたのは昭和30年(1955)頃であったという。
宝滝酒造の創業は江戸時代末期に初代・中野勘歳という人が様々な商いを経験したのち帰郷して、濁り酒の醸造を開始したことから始まっている。その後、清酒に切り替え下閉伊酒造組合が設立する昭和33年(1958)頃まで製造を続けた。宝滝の原料は現在の紫波郡都南村から産出する「とくた米」という醸造に適した米に、古くから中野家に伝わる長沢川へ流れ込む地下水脈を井戸で汲み上げて仕込み水としていた。晩年は酒造りの時期になると石鳥谷から社氏が訪れ後期の昭和32年(1957)頃には約250石の清酒を仕込んでいた。 宝滝の名前の由来は長沢街道の西の果てにある川目地区よりさらに深い山懐にある鵜ノ主滝(うのしゅのたき)という幽玄の滝から命名したもので最初は「七滝」という名称だったが、当時全国に約5000軒あった酒屋が製造する酒に同じ名前があったことから「宝滝」と名称変更された。
今は醸造されていない清酒・宝滝は 一級、二級とも口当たりはピリッとしてノドごしは甘い独特の旨味で観評会では何度も受賞している。全盛期には計り売り、ビン売りの他、一斗樽、四斗樽でも販売され、小売専用の店舗を別に開業したほとであった。その人気は現在の地酒・千両男山と二分する勢いで、宮古下閉伊の消費者に愛され続けたが、太平洋戦争、終戦後の物資不足、そして大蔵省の全業整備により昭和35年(1960)下閉伊廼造組合に統合し宝滝の名は失われた。
創業は江戸末期の万延元年
- 清酒・宮古川
宮古川は本町の東屋酒造で醸造されていた酒で、東屋三代目の菊池長七氏という人が江戸時代中期に創業を開始した。正確な年代ほさだかではないが、江戸末期の万延元年(1860)に南部藩が東屋宛に200石の酒造の許可を許した証文が現存することから、その歴史はさらに深く、おそらく宮古で最も古い造り酒屋であったと思われる。
宮古川の名称は宮古の中心を流れる閉伊川にあてた名前で、清らかで悠久な品質へ の願いが込められていたという。宮古川醸造に使用された米は塩釜から船舶で運んだものだが、宮城米であったかどうかはわからない。仕込み水は東屋敷地内にあった井戸から汲み上げた地下水で、品質、水量ともに宮古では有数の名水であったという。
仕込みは毎年11月から翌年の3月頃までで、石鳥谷、佐羽根などから杜氏を招いて製造していた。宮古川の味は辛ロで並と上に分類されていた。販売はほとんとが4斗樽による卸と店頭での計り売りが主で、ビンに詰めて販売したのは大正時代に入ってからだという。また、宮古川では酒をしぼつた後に残る酒粕を利用し焼酎も製造していた。焼酎は粕焼酎という総称販売されていたが当時名称を登録しておらず、口当たりは独特なクセと匂いがあったが、清酒より安価なため消賞者には喜ばれたという。
昭和初期頃には宮古町に市が立つ日、祭、馬や牛の競りがあると、近郷近在から宮古を訪れる人々が東屋酒店の店先で計り売りの宮古川を飲んだ。なかには店先で弁当を広げ宴会をほじめる家族もあったという。 そんな宮古川も情勢緊張が続いた昭和16年(1941)頃から酒の醸造を縮小、戦時中には完全に中止してしまう。その後、敗戦の物資不足に加え、政府が指導した企業整備のため、昭和30年(1955)、八代目の菊池長七氏の時代に下閉伊酒造組合に統合、その長い歴史に祭止符を打った。現在の東屋は当時から酒蔵として利用していた蔵のみを残して、その他の蔵は数年前に撤去、宮古川の仕込み水であった井戸は鉄板でふたをして駐車場となっている。
千石船の船名を戴いた辛口
- 清酒・虎一
江戸末期の頃太平洋航路が拓けると、南部藩御用船として宮古港からコンブやワカメなどの海藻をはじめ干魚、魚油、魚糟などの特産品を江戸へ運び、帰り荷で江戸で買い付けた品物を満載して往復する「虎一丸」という千石船があった。この船は津軽石の豪商・盛合家が建造し南部藩に献上、これを藩から貸与するかたちで宮古-江戸間を往復する廻船問屋として商売をしていたものだ。この千石船の名を冠名にしたのが、津軽石盛合酒造で製造されていた清酒・虎一だ。
虎一の製造年代は不明だが、江戸末期頃で盛合家31代目の盛合光蔵の時代だったらしい。酒造のきっかけは宮古の漁船が沖で操業する際、漁夫の身体を温めるために酒の醸造許可を南部藩に求めたと伝えられている。名前の由来は藩政時代に宮古・江戸を往復した千石船虎一丸の船主だったことによる。
虎一の原料となる米は紫波米をはじめ県内産の米を僕用し、毎年12月から翌年3月まで北上の杜氏が丹精込めて磨いた。仕込み水は盛合家で古くから飲替水として使用していた、津軽石川へ流れ込む湧き水を使用したものでその水は現在でも水量の衰えはない。 酒の醸造仕込みには儀礼的な部分が多く、杜氏は醸造の守り神として信仰される松尾神社の祭壇を祀りその部屋には経営者でさえ立ち入ることを許さなかったという。
虎一の特徴は特級、一級、二級とも一貫して爽快な辛口が特徴で、そのキレ味は海の男をイメージするものだった。全盛期には縁起のよい名前と飽きのこない味が漁業関係者に喜ばれ船積み用の酒として大きな発注もあった。その生産高は昭和32年(1957)の資料によると350石で宮古・下閉伊管内では千両・男山に次いで二番目となっている。しかし順調だった虎一も財務省の企業整備のため昭和35年(1960)下閉伊酒造組合に統合され姿を消した。
財務省の企業整備で発足・下閉伊酒造組合
- 清酒・宮霞・濱菊
下閉伊酒造組合は、昭和9年(1934)に財務省(当時の[1])が指導した酒類企業整備により宮古・下閉伊地区に存在した6カ所の造り酒屋が統合されて昭和30年代初期に設立したものだ。当初宮古市千徳のJR千徳駅前に拠点工場を構え宮霞(みやがすみ)濱菊(はまぎく)などの清酒を醸造してた。戦後になり様々に経営系態を組み変えながら生産を続けたが、昭和46年(1971)「岩手桜顔酒造」に統合された。
宮古における藩制時代の酒造り
江戸末期の古文書から酒について調べると、宮古にも数軒の造り酒屋があったことがわかる。それら造り酒屋の詳しい創業や石高についてはわからないが、その時代に酒屋を経営ずるということは、その土地でのかなりの有力者であるということは事実のようだ。
酒造りは南部藩に納める「役金」「運上金」「補金」によって許可が下りた。この金額は当時とすれば莫大なもので一般の商いをしているものが払える金額ではなかった。また、仕込みに使う米も馬で運ぶ程度ではなく、遠くは秋田などから船舶を使用し運ばれたことから、当時としても大掛かりな先物取引であった。 製造される酒は清酒の他、にごり酒なとで現在のようにビンなどがないため、酒屋の店先で計り売りしたり、振り売りといって天秤棒に酒桶をぶら下げて行商もしていた。
現在もそうであるように、酒類には大幅な税金(役金)が加算されており、価格は藩内では一定だったが、飢護になると原料の米の価格が値上がりりするためぺべらぼうに小売価格が上昇して消費者を苦しめることもあった。また、飢護が続くと酒造りそのものを藩が停止させる場合もあり、役人らは造り酒屋の道具などに藩の書面が普かれた封印を貼り、隠れて使用されないように厳しく管理した。
関連事項