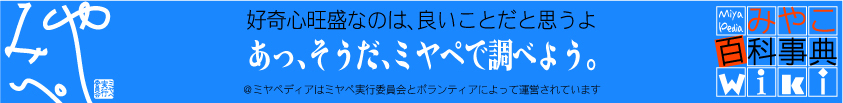2012/10 残暑の秋、高新氷を思い出す
今年は盆過ぎだと言うのに秋風どころかまったく衰えない太平洋高気圧の熱風で秋の虫すら啼かなかった。そんな猛暑になると昭和時代に食べたかき氷だ。今月はちょっと季節外れだがかき氷の思い出を書いてみよう。
夏に削った氷を食べた記録は『枕草子』に記載があるというから平安時代ではあるが、夏に凉を求め一般人が氷を口にしたのは自然貯蔵型の氷ではなく製氷技術が発達した明治後期から大正期であったと思われる。宮古においては代議士・篠民三若かりし頃の明治8年に民三が閉伊川の水を使った製氷工場を作り氷を東京へ出荷し「タイシタ/ずいぶんと」大儲けしている。しかし、この氷は魚を冷やす氷であり衛生的にも人が口にできるものではなかったようだ。結局、宮古でかき氷を食べるようになったのは飲料水を使って製氷がはじまった昭和10年前後「ダーベーガ/じゃないかな」と推測される。ただしこの頃のかき氷は「マヅバ/町場」の氷屋から氷を買ってきて家庭で作っていたもので、飲食店で夏場の限定メニューとして売られるようになったのは終戦後であろう。当初、かき氷は氷鉋とよばれる木工カンナを裏返しにして脚を付けたような道具に氷の塊を載せて布巾で押さえて前後運動で削りそれを下から「エレモンコ/器」で受けていた。そこから氷を固定し回転させて削るかき氷機が考案され後に手動から電動へと進化した。この機械は涼しそうな柄が透かしになった鋳物製のフレームにペンキが塗られ、僕が子どもの頃(昭和30年~40年代)はほとんどのの飲食店が使っていた。
かき氷のメニューは色々あるが王道はなんと言っても「いちご氷」であろう。価格は年代により様々だが、昭和30年代で5~10円ぐらいでその後の物価上昇に比例して30円、50円、100円と値上がりした。いちご氷に甘い練乳をかけたのが「いちごミルク」だ。こちらはいちご氷の3~5割高の価格設定だった。昔はサッカリンやチクロなどの合成甘味料、合成着色料が満載のシロップで食後は「スッタ/舌」が「マッカグ/真っ赤に」なって見せ合いをしたものだ。その他の定番はザラメ糖を溶かした氷蜜に練乳をかけた「ミルク氷」、甘く煮た小豆が入った「あずき氷」甘く冷たい白玉団子と小豆が入った「白玉氷」などがあった。昭和40年代には氷シロップも種類が増えて黄色の「レモン氷」緑の「メロン氷」などもあたが所詮は無果汁であり「イロベー/色だけ」良くて味はたいしたことなかった。
氷屋は夏になると繁盛し寒くなれば客足は遠のく。これと逆なのが暑いと客足が遠のくラーメン屋であった。昭和40年代、町の食堂や中華そば屋にエアコンどころか扇風機さえなかった。そんなある猛暑の夏、向町の交差点にあった、老舗たらふく食堂では開店以来、中華そば一本でやってきたがその年、一年だけかき氷を出したという。これは現在のたらふく食堂の主人に聞いた逸話で、開店以来中華そば一本でやってきた同食堂の唯一の複合メニューだったらしい。思うにこれは同じ向町にあった、かき氷専門高新氷店の繁盛に触発されてものだろう。
さて、老舗たらふく食堂すら夏場は観念したという、今は無き高新氷店はメニューのすべてがかき氷という特殊な専門店だ。そのメニューはまさに星の数まではいかないにしても100種近いメニューが並んでいた。場所は向町の自転車屋の隣で、当時の若山医院入り口の「スズムゲー/筋向かい」だった。入口はドア一枚だったが「ホソケー/細い」「ローズ/通路」を経て店内に入ると中はかなり広く奥には小さな座敷もあった。窓はなく空気はどんよりしていて甘いシロップの匂いが立ちこめていた。テーブルにはビニールが敷いてあり客がこぼしたであろうシロップでどことなく「ネッパッテ/ねばねばして」いた。それでも昭和40年当時、みやこ夏まつりを港まつりなどと呼んでいた頃は宮古橋からの花火見物の帰りや、秋の「ハズマンサマ/横山八幡宮」の「ヨミヤ/宵宮」には超満員だったし、夏はクラブ活動帰りに寄る高校生も多かった。この店の看板メニューは、初恋氷、アベック氷、コーヒー氷などの色物も有名だったが、何と言っても強烈なのが大皿に10人分はあろうかという量の各種かき氷と缶詰フルーツを盛り込んだチャンピオン氷だろう。もちろんこれは一人で食べるものだはなくグループで注文しみんなでワイワイ食べる特殊なかき氷だ。価格は時代により変動したが確か2000円ぐらいで、チャンピオン氷をひと回り「ツッツァグ/小さく」した少人数用のジャンボ氷というメニューもあったと記憶している。この時代、少年マガジンが90円だったから子どもにとって2000円クラスのかき氷は高値の花で僕は一度も挑戦したことがなかった。また、当時はディスカバージャパンなどの旅行ブームもあり多くの旅行者が宮古を訪れ、高新氷店の異空間でチャンピオン氷と格闘した。その逸話は神話となり、知る人ぞ知るかき氷専門店としてその名は全国に知れわたっていた。
そんな高新氷店も消費者ニーズの多様化、長年続いた冷夏などで客足が遠のいてゆく。そして1990年代前半、その長い歴史に幕を引いた。それはとある年の初夏であった。かき氷を食べるにはまだ早い時期に、高新氷店の入口に達筆な文字で綴った貼り紙があった。そこには店主の高齢化による閉店の知らせとこれまでの感謝が綴られていた。思わず僕はこれを写真に撮った。こうして宮古、いや県内、いやいや、全国的にも珍しいかき氷専門店はひっそりと閉店した。現在、東日本大震災による津波で向町はがらんどうのままだ。旧宮古橋を下りて向町に立つと遠く常安寺の方の山で啼くセミの声とともに、まさに激動の烈夏であったあの頃の夏と、高新のかき氷を思い出すのだった。
=懐かしい宮古風俗辞典
ざっつぁます
雑回し。サイズや用途が特殊で片付けようがなく邪魔なもの。
長くもなく「ミツカグ/短く」もなく「オボダクテ/重くて」「ツッカゲドゲバ/立て掛ければ」転ぶ…。片付けたくとも片付けられず、さりとて「ヤグニモタヅヤガンネー/役にも立たない」が捨てるには惜しい。しかし、そのままにしておけば利用価値は極めて低く邪魔で移動させようにも場所をとって困る…。例えば何年も前に亡くなった祖父が昭和時代に買いそろえた日本文学全集、今は嫁に行った娘が使っていた旧式のエレクトーン、昔息子が熱中していたウィンドサーフィンのボードなどなど家中探せば潰しのきかない趣味的道具がわんさか出てくる。そして「アーリイェイ/まったくもう」と腕組みするお母さんの周りには、通販で買って三日坊主で辞めた美容健康機器、クローゼットを片づけるつもりが逆に散らかしてしまうおかしな形の回転ハンガー、買ったはいいが数回しか使っていない野菜カッターなどこちらも「ザッツァマス」のオンパレードだ。けれど、今は出番がなく使わない物でもいつかは役に立つ日がくるだろうから何も今すぐ「フテナゲル/破棄する」こともあるまい。ただ、何処へ置いてもやはり「ザッツァマス」なわけで気が滅入ってしまう。欲しい人がいたらあげたいけれど、こんなガラクタ貰う人なんていないよね。